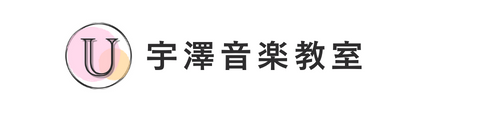ICT機器との向き合い方 -教室としての指針-
今日も宇澤音楽教室のブログをご覧くださり、ありがとうございます☺️
今日は「宇澤音楽教室の中でICTをどう使うか」について、私の考えをお話ししたいと思います。
❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁
2019年から、日本の学校教育ではICT(情報通信技術)機器の活用が本格的に推進されてきました。
「日本の学校音楽教育とICT活用」の分野で教壇に立っている立場上、国や大学の方針に逆らうことはできませんが、
沢山の情報を収集していますので、メリットと同時にデメリットについても日々、考察しております。
ICTには確かに多くのメリットがあると実感しています。
たとえば、動画教材やクラウド型の課題提出システムは、教員にも学生にも便利です。
オンライン授業によって、遠方からでも質の高い学びにアクセスできるようにもなりました。
教育の可能性が広がっているのは事実です。
しかし一方で、ICTの利用には慎重さも必要だと私は考えています。
教育先進国として知られるフィンランドやスイスでは、ここ数年、子どもたちの思考力や集中力の低下が問題視されるようになりました。
子供たちはマルチタスクをうまく熟す能力を持ち合わせていないため、タブレットでの学習は「本来、自分がやるべきこと」からの集中がそれ、結果として質の良い学びを行えないなどの障害がでます。
フィンランドでは、国(政府)として「学校教育の中でのタブレット(液晶)の使用を制限し、紙ベースの学習へと回帰する方針」が検討され、つい先日もロイター社がニュースを出していました。
教育にデジタル機器を取り入れることで、便利さと引き換えに「考える力」や「じっくり取り組む力」が奪われてしまっているのではないか。
また視力の低下や液晶と長時間向き合うことによる健康上の問題がでてきます。
❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁
宇澤音楽教室でも、ICT機器は一部活用しています。
生徒さまが自分の演奏を録音・録画して振り返ったり、液晶画面に書き込みを行いドリルを解いていただくこともあります。
小さいお子様のレッスンでは、タブレットでリズムなどの説明をするとワクワクしながら集中をして見てくださるので、難しい内容でも比較的すんなりと理解してくださいやすいように思います。
ただし、使う場面はあくまで限定的にしたいと考えています。
音楽の学びにおいて大切なのは、耳で聴き、心で感じ、身体で覚えるという、人間本来の感覚です。
それらはデジタル機器だけでは育まれません。
ピアノを通じて得られる深い集中や、人との呼吸の合ったアンサンブル、舞台の緊張感の中で発揮される表現力
——こうした体験の中にこそ、「生きた学び」があります。
ICTは便利な道具です。
でも、それが教育の目的になってしまってはいけません。
どのように使うか、どのタイミングで使うか。
その判断こそが、私たち教育に携わる者に求められていることなのだと思います。
今日もWebサイトをご覧くださり、ありがとうございました😊