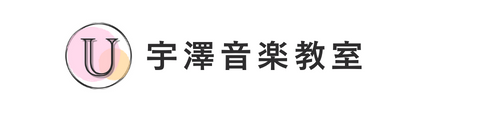子どもたちを「見せる」より、「守る」ことから始める音楽教室のかたち
最近、InstagramなどのSNSで、子どもたちのレッスン風景や演奏動画を積極的に発信している音楽教室を多く見かけるようになりました。演奏する子どもたちの姿はたしかに愛らしく、その一生懸命な表情や響く音には、思わず見入ってしまいます。
けれども、私はその風潮にどこか違和感を抱いています。
もちろん、それぞれの教室に、それぞれのやり方や考え方があることは承知の上です。
でも、ひとつ気になっているのは、「その子どもたちは本当に、動画に載せられることを心から望んでいるのだろうか?」ということです。
子どもたちは、思っている以上に大人の期待を察する力を持っています。「嫌だ」と言うことで、先生や親にがっかりされるのではないかと不安になったり、自分の気持ちよりもまわりの空気を優先してしまったり。
そういったことが、小さな心の中で起きているかもしれない……私はそう想像してしまうのです。
さらに、東京という情報が密集した場所では、顔を隠していても服装や演奏曲、背景などの情報から、個人が特定されてしまうリスクもあります。音楽教室という、安心して自己表現を学ぶべき場所で、子どもたちが無自覚のまま「見られる存在」になることに、私は慎重でありたいと考えています。
宇澤音楽教室がSNSに生徒さまの動画を載せない理由
宇澤音楽教室では、レッスン中の動画をSNSに掲載することは一切していません。それは、単なる方針というより、私自身の教育に対する信念です。
子どもたちにとって、音楽とは「誰かに見せるためのもの」ではなく、「自分自身と出会う手段」であってほしいと願っています。
その営みは、静かで個人的で、そしてとても尊いものです。
教室の中で、思うように弾けなかった日も、ちょっとふてくされた日も、思いがけず音楽がひらいていった日も、すべてはその子の成長の過程です。
それを無理に「発信する価値」として切り取らず、ただ丁寧に見守ること。
それが、私の仕事であり、責任だと思っています。
子どもたちを「守る」ことが、やがて信頼になる
このような姿勢が、結果として保護者の皆様の安心につながっていると感じています。
動画や写真がなくても、教室には地域の子どもたちが自然と集まり、親御様同士のあたたかなつながりも生まれています。
子どもたちの演奏姿は、たしかに美しい。
けれど、その美しさは「守られている場所」でこそ咲くものです。
これからも私は、子どもたちの「音楽と向き合う時間」を、静かに丁寧に守り続けたいと思っています。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。