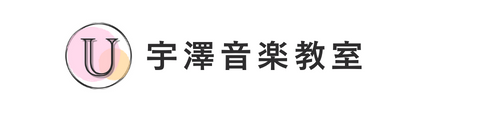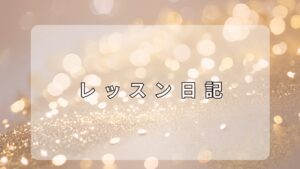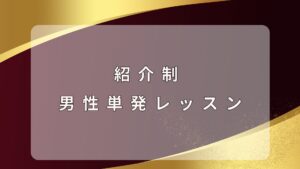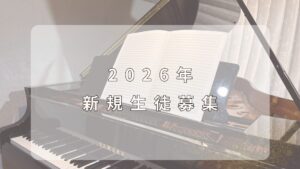11月18日(火)のレッスン日記
💖5歳の生徒さま
ル・クーペのピアノの練習ABC 、スカルラッティの小品などに取り組んでいます。
先週、出させていただいた宿題を両手で演奏してくださいます👏
今月末には完成させられそうですね。
不思議な力(才能)をもっている生徒さま。
丁寧にしっかり力をつけていただきたいです。
【紹介制】男性単発レッスン開講
上質な時間を求める大人の方へ
“日常の中に、静かで豊かな芸術の時間を持ちたい方”に、
落ち着いた環境で質の高いレッスンをご提供いたします。
🔹静かに集中できる時間を持ちたい方
🔹憧れの曲を確かな技術で仕上げたい方
🔹基礎を整え、より洗練された演奏を目指す方
🔹グランドピアノのある場所で思考を整えるひとときを求める方
11月17日(月)のレッスン日記
今日も宇澤音楽教室のブログをご覧くださり、ありがとうございます😊
本日より『今月のレッスン日記』を書いてまいります😊
毎月のレッスン日記では今月にチャレンジできたこと、そして、来月の目標を共有することにいたしました。
2026年 定期レッスン 新規生徒募集♩(申込終了)
11月15日より2026年の定期レッスン新規生徒募集を行っておりましたが、12月7日をもってすべての枠の確約をいただき、募集を終了いたしました。
多くの方からご要望をいただき、心より感謝申し上げます。
ご希望に添えなかった方もいらっしゃいますが、また別の機会にご縁がつながりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
レッスン日記:9月12日(金)の音楽
💖小学5年生の生徒さまレッスン
発表会前に少し行き詰まりを感じているように感じられます。
本番が近づくと無性に不安になり、いつものように弾けないということはあり得ます。
技術的にできなくなっているのではなく、気持ちが焦ってしまうが故に、テンポが速くなってしまったり。
弾けないことが不安になり、不安を解消できないまま時が過ぎるので良い練習ができないこともあります。
発表会やコンクールといった本番は出ることだけが全てではありません。
その機会を経験する中で、不安になったり、緊張したり。
そういう「マイナスの感情とどのように向き合うか?」も音楽レッスンの一部です。
楽譜の裏側に、目一杯本番前の考え方や練習の仕方を書きました👍
レッスン日記:9月9日(火)の音楽
💖高校2年生の生徒さまレッスン
ベートーヴェンのピアノソナタに取り組まれています。
The Beginning of Beethoven in My Life
そういう気持ちで本番を迎えていただきたいと思います。
「ソナタはピアノを続けている限り、何歳になっても味わえる楽曲だと思うから
今回の発表をゴールとするのではなく、通過点として捉えてほしい」とお伝えしました。
レッスン日記:9月8日(月)の音楽
💖小学5年生の生徒さまレッスン
みなさんのびのびと自分の考えを伝えてくださいますし、誰一人として同じように育っている方がおりません。
みんな『松』のように育っています。
誇らしいです😊
「自分で選ぶ」ことは学習意欲を高め、音楽をより自分のものにしていく大切なプロセスです。
レッスン日記:9月7日(日)の音楽
💖 中学2年生の生徒さまレッスン
計画的に楽曲と向き合っています😊
8月で「黒鍵のエチュード」を両手で演奏できるようになりました👏
今日から17日までは片手のみ。
17日から発表会までは黒鍵の練習はなしで発表会曲に集中🎶
”発表会の翌日”から黒鍵を片手ずつ再開するというスケジュールです📌
バルトークの楽曲はもうひとふんばり。
改めて楽譜に書いてあることを細かく、確認をしてまいりました。
お教室に通われた時がはるか昔のようですが、教室に通われてからの生徒さまの成長っぷりは素晴らしいものです。
レッスン日記:9月5日(金)の音楽
今日も宇澤音楽教室のインスタグラムをご覧くださり、ありがとうございます😊
本日は台風15号が接近し、警報がでておりました。
朝、親御様にご連絡をし、「レッスンの振替」をご提案させていただきました。
結局、18時ごろには雨も止んでおり、心配するほどの雨ではなかったものの、安全な時にレッスンに来れるならば、心理的にもその方が良いかと思います😊
宇澤音楽教室の振替制度は通われる皆様にとって通いやすいように設定させていただいています。
レッスン日記:9月2日(火)の音楽
💖5歳の生徒さまレッスン
レッスンの最初は「指づくり」から始めました。
指づくりは毎日の少しの積み重ねが大切です。短い時間でも毎日続けることで、弾く音の透明感や響きが大きく変わってきます🎵
10〜15分かけても良いくらい大切な練習ですが、今日は5分弱で終えましたので、お家でもぜひ継続していただきたいです。
毎回行うエクササイズは少しずつ内容を変えて、飽きずに取り組めるよう工夫しています。
今日はモーツァルトが6歳の時に書いたとされる『メヌエット』に挑戦👏