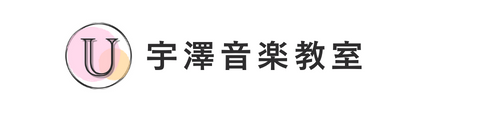レッスン日記:3月14日(金)の音楽
💖大学生の生徒さまレッスン(より抜粋)
今日は「ピアノ演奏と視線の研究」についてお伝えしました。前にも触れたことがあります。
センサーの技術が発達してから、視線研究は現在においても活発に行われていて、定量的な結果がでてきています。
科学的根拠をもって、「どこをどのように見た方がよいか?」をお伝えできます。
視線だけではなく、それに伴って手も準備できると弾きやすさが何倍も変わります。
色々な論文がでているので、ぜひ、検索して読んでみていただきたいと思います😊
レッスン日記:3月10日(月)の音楽
💖高校1年生の生徒さまレッスン
バッハ、ベートーヴェンともに両手譜読みにチャレンジくださっています。
バッハに関しては、「両手で読んだ後に改めて1声部ずつ確認して、どの声部が主題(テーマ)を受け持っているか?を確認して、改めて両手で演奏しよう!」とお伝えしています。
ベートーヴェンに関しては、「ショパンエチュードとの繋がりを感じた」というコメントを伺った後に、和音で掴む練習方法をお伝えしました。
和音で掴む練習は、時代やジャンル問わずに活かせる練習方法ですので、今後も取り入れていただきたいです。
今週発表のディズニーの楽曲は本日合格にいたしました😊
ディズニーの曲といっても、生徒さまが取り組まれてきた楽曲の中でも難易度が高かったのではないでしょうか?
この曲を通して、「弾く」ということだけではない学び(コードやストーリーの作成)や、内声部のメロディの出し方やショパンやラフマニノフに通じる響きの生み出し方、フランス近現代のピアニズムなど多岐に渡る学習をしていただけました。
レッスン日記:3月9日(日)の音楽
💖小学6年生の生徒さまレッスン
生徒さまはショパンの「黒鍵のエチュード」やリストの「ラ・カンパネラ」を弾きたいという夢があります😊
「そのどちらも練習曲であり、易しい楽曲ではにゃいね〜!🐈」と伝えて、「そこに至るまでに乗り越えたいこと」についてもお話しました。
ロマン派の練習曲は、突然生まれたわけではなく、生まれた背景がありますので、そうしたことも軽くお話ししました。
譜読みが早く、パッとその場で弾く力あります。
その力に加えて、「属調や下属調に転調するだろう」「ここは近親調の和声だ」といった予測ができるようになると、もっと譜読みがしやすくなります。
一音一音読むのではなく、和声で捉えることができれば、譜読みは何倍も早くなります。
さらに和声の仕組みさえわかれば、暗譜も早くなります。
練習曲を単純なる練習曲にするのではなく、和声の機能を学ぶ教材としても活用したいと思います📕
抜粋
♪ ピアノ弾きあい会 レポート ♪
【心温まる音楽の贈り物】
小学生を対象にした「弾きあい会」を開催しました。
第3回目の弾きあい会は来週開催予定です。
この記事では、弾きあい会のレポートをお届けいたします😊
(中略)
音楽の素晴らしさは、分かち合うことでより一層輝きを増すのだと、改めて感じさせられました。
今後もお子様たちの音楽への情熱を育んでいきたいと思います。
皆様のご支援とご理解に、心より感謝申し上げます。
温かい音楽の輪が、宇澤音楽教室を益々温かくしてくれています。
レッスン日記:3月7日(金)の音楽
💖小学4年生の生徒さまレッスン
今回は「調と和声の原理をもとに、次に出てくる音を予測しながら譜読みを行う」という、知的な取り組み方をしていただいています。
あら、不思議✨
どんどんと弾ける箇所が増えていきました😆
専門性の高いレッスン。
ただただ楽譜を読むのでは時間が足りません。
やりたいことを最速で叶えていきます😊
レッスン日記:3月4日(火)の音楽
小学4年生の生徒さまレッスンより抜粋
弾きあい会は、グループの中でのみんなの個性を知れたり、人前で演奏した時に現れる音色、みんなの率直な意見(講師として生徒さまの成長のために改善した方がいいこと含め)を知れて、とても有意義でした。
「エリーゼのために」に長期的な目線で取り組みつつ、美しい響きを奏でる指づくりを連弾を通して、音をよーーーく聴きながら行っていきます。
今日はピアノの内部もお見せして、仕組みまで把握していただきました。
「シーソーと同じ原理だ!」と気づいてくれました。
さすが理科が好きなお子様!
学力はピアノに活きてきます😊
小学生ですが、原理からお伝えして、頭と耳と指(体)すべてを使って、「美しさ」を追求していきます。
レッスン日記:3月3日(月)の音楽🎶
💖高校1年生の生徒さまレッスン
期末試験が4日連続である中、試験中もしっかりとピアノの練習ができています👏
というよりも、練習しない日がないという素晴らしい習慣をお持ちです。
本当にすごい👏
どんどんどんどん上手になって、本当に驚かされます。
バッハの楽曲は、全音の楽譜通りに弾いたあとに、山崎孝さんが編集した装飾でも弾いていただきました。
これぞ、ギャラント様式。
色々なエディションを試し弾きできして、バロック時代の音の華やかさや上品さを感じていただけたと思います。
また「楽譜に書いてあることを過信してはいけない。音楽の世界はもっと深い」という話もできました。
レッスン日記:3月2日(日)の音楽
💖小学6年生の生徒さまレッスン
今日のレッスンでは学校での曲やショパンのワルツを聴かせていただきました😊
「譜読みを上手に省略する」ことが早く譜読みを進めるコツです。
強弱を感じていただくために演奏も聴いていただきました🎵
「楽曲に取り組むだけではなく、練習曲のようなものも導入した方がいいと思うよ〜」とお伝えしています。
💠音階練習
💠アルペジオ練習
💠半音階
💠同音連打
💠3度・6度
このあたりは、全てのプロ・アマ問わず全てのピアニストが行っている練習です。
レッスン日記:2月21日(金)の音楽
指遣い(フィンガリング)は、ピアノ演奏においてとても大切です🎵
適切な指遣いを選ぶことで、スムーズなフレーズの流れ、正確な音の発音、音楽的な表現の自由度が大きく高まります。
逆に、無理な指遣いをしてしまうと、演奏がぎこちなくなり、テンポや強弱のコントロールが難しくなります 。
色々な方が指遣いについて言葉を残しており、数えきれませんがご紹介いたします。
⭐️ショパン
「正しい指遣いなしには、美しい演奏はありえない」
ショパンは指の自然な動きを尊重し、弟子に伝え残しています。生徒さまへは文献をもとにご紹介しています。
⭐️アルトゥール・シュナーベル
「指遣いは単なる機械的なものではなく、音楽を形作るための手段である」
シュナーベルはベートーヴェンの演奏で有名なピアニストです 彼もまた、指遣いが音楽的表現に直結することを強調しています。
ポップスやジャズにおいても、指遣いは重要視されています。
⭐️ビリー・ジョエル
「指遣いを間違えれば、フレーズが崩れる。クラシックもロックも同じだよ」
⭐️エルトン・ジョン
「ピアノはただ弾くものじゃない。指の動きが音楽の流れを決めるんだ」
レッスン日記:2月20日(木)の音楽
2−3月は勤務している大学がお休みですので、木曜日に振替レッスンをすることがございます。
❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁
💖小学2年生の生徒様レッスン
今日は取り組んでいる楽曲のほか、ポップスの楽譜を読みながらリズムの学習をしたり、1年間を振り返ったり、さまざまなことを行いました🎶
「鍵盤が手元になくても、指のトレーニングはできるよ」とお伝えし、そのやり方と注意点をお伝えしました✨
「いつ、どのタイミングで、どのトレーニング方法を、どのようにお伝えするか? 」
単調なトレーニングは絶対に必要ですが、すっごく楽しくはありませんので、楽しさとの両立が難しいところですが、関心や意欲が高まってる時にお伝えしています。
もちろん、基本的なことは最初の月にお伝えし、姿勢や指先の意識などは毎回、皆様にお伝えしています。